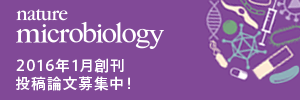PJ-182:共生菌(糸状菌)の細胞壁成分を指標とした定量
1筑波大学, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
【はじめに】エンドファイトとは、植物体内に顕著な病徴を示さずに生活する微生物で狭義にイネ科草本に共生するバッカクキン科の糸状菌を指す。植物体内で植物に病徴を示すことなく生活するエンドファイトの植物体内量と植物の分化・生長の関係について詳細に調べるために、植物体内に存在する共生菌の正確な定量が必要となる。我々は、(GlcNAc)2 (N-アセチルグルコサミンダイマー) を主な分解産物とする糸状菌細胞壁構築成分(キチン)を酵素を用いて、これを定量することで、種子及び芽生え中のエンドファイトの存在量を、菌体相当量として算出する定量法を確立してきた。今回、本手法を利用して定量を行った例を示し、生態研究における本手法の汎用性について考察した。現在、エンドファイトの存在量は、主に菌のタンパク質や遺伝子を指標として調べられているが、糸状菌細胞壁構築成分(キチン)を指標とした方法は、菌体量に直結する正確な定量が期待できる。
【方法】共生菌が感染しているトールフェスク、ネジバナおよびサクラを本研究の対象材料とした。植物を採取し、基質となる細胞壁画分を調製した後、酵素(キチナーゼ)処理し、分解産物を得た。分解物について、還元化反応を用いて還元糖に化学的修飾を施した。既知共生菌乾燥重量に対する既知共生菌の細胞壁分解量の検量線作成をした後、HPLC分析により、(GlcNAc)2の定量分析を行い、対象とした糸状菌相当量を算出した。
【結果および考察】試みた対象材料について、細胞壁構築成分を指標として、共生菌の相当量を算出することが可能であることが分かった。この時得られた(GlcNAc)2は、ポジティブモードのLC-ESI/MS分析により確かな分子量を示したことから、HPLC分析で簡便に生体内共生菌の存在量を調べることができ、生態や生長・生理分野の研究で利用するのに汎用性は高いと考えられる。平行して対象宿主生物と親和性の高い共生菌の生化学的・遺伝的情報蓄積を行い、今後、これまで用いられてきたタンパク質や遺伝子を指標とした手法とを融合することで、より詳細な共生菌量の定量が可能で、双方の生長過程における情報伝達に関与する物質(群)に関する新規情報を得られる可能性があると考え進めている。
keywords:Endophyte,(GlcNAc)2,Quantitative analysis,,,