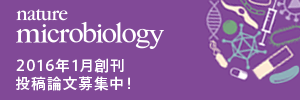PC-047:森林の土壌微生物群集の1年
1東京大学, 2北海道大学, 3京都大学
土壌微生物の増殖や死滅、様々な代謝反応は森林生態系の生産性や維持に大きく寄与している。微生物の増殖と死滅はそれぞれ、土壌中の炭素や窒素の菌体内での保持と菌体外への放出と捉えることができ、また窒素化合物の形態変化の多くは特定の微生物代謝である。そのため森林生態系において微生物群集の量や代謝能の変化は炭素・窒素循環への寄与を介し、森林生態系の形成に大きく関わることが予想される。そこで本研究では、森林土壌中の細菌や真菌ならびに窒素循環に関わる微生物群の量的な変動と細菌組成の変動を1年のスケールで明らかにすると同時に、それら変動が炭素・窒素循環へどのように反映されるのかを明らかにすることを目的に調査を行った。
本調査は京都大学北海道研究林標茶区にて行った。10日から2ヶ月に1度の頻度で土壌を採取し、各種土壌理化学性の測定とともに微生物DNAを抽出した。続いて全細菌・古細菌の16S rRNA遺伝子、全真菌の18S rRNA遺伝子、アンモニア酸化細菌(AOB)およびアーキア(AOA)が有するamoA、脱窒微生物が有するnirKの定量を行い、各微生物群の量的変動を解析した。16S rRNA遺伝子については大規模シーケンスにより細菌組成の変動を解析した。
全細菌・古細菌の16S rRNA遺伝子量と全真菌の18S rRNA遺伝子量は共に冬期に増加し、春先に減少するというパターンを示した。これは土壌中の有機態炭素濃度の変化と同様のパターンであった。このことは春先における微生物群の死滅が土壌への有機態炭素ならびに窒素の主要な供給源となっている可能性を示している。続いてAOBのamoAは冬期にのみ顕著に増加する一方でAOAのamoAは減少した。AOBのamoAの増加は総硝化速度ならびにアンモニウム濃度の増大と一致しており、AOBが主要な硝化微生物群であると同時に、1年を通して冬期が硝化の活発におこる時期であることを示唆している。春先にAOBのamoAが減少した後、nirKの増加が見られた。春先には土壌中に硝酸イオンが蓄積すると同時に雪解けにより土壌の水分量が増大するため、この時期には脱窒が活発になっている可能性が考えられた。このように微生物群は1年を通して量的な変動を示したが、シーケンス解析の結果、優占細菌群の組成は1年を通してほぼ一定に維持されていることが示された。
keywords:土壌微生物,硝化,脱窒,森林,,