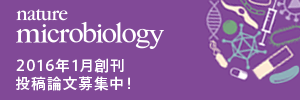PB-037:水田からのメタン発生量の増減に伴う土壌古細菌相の変化
1農環研, 2太陽計器(株)
[背景]水田は温室効果ガスのメタンの主要な発生源の一つであり、メタンの多くは土壌古細菌によって生成されている。その一方で、水田にはメタン生成菌以外にも様々な生物が生息し、相互に影響していると考えられる。本研究では、生物の増減を水田土壌のメタンフラックス等の環境データと照合することで、メタン発生に関わりの深い生物を推測する。まずは、メタン生成菌を含む土壌古細菌について解析を行った。
[方法]つくばみらい市水田圃場のメタンフラックスをチャンバー法で経時的に測定した(2012年)。同年に同水田からコアサンプラーで土壌を2週間ごとに採取し、表層土(0〜1cm)および下層土(2.5〜5 cm)の二価鉄量と土壌pHの推移を測定した。メタン発生前、発生初期、最発生期、減少期、落水期の5時期の下層土と発生初期と最発生期の2時期の表層土からDNAを抽出し、16S rDNA配列の次世代シークエンス解析(454 GS Jr)を行った。
[結果] 5月末の田植えの後、6月中旬頃からメタンの発生が認められ、8月初旬に最大となり、8月中旬にはやや減少した。二価鉄量は湛水期間が長い程多くなり、8月末の落水で大きく減少した。下層土では、古細菌rDNAのうちおよそ4割がEuryarchaeota門に由来し、Methanoregula属、Methanosaeta属、およびMethanocella属が高い割合で検出された。Methanoregula属は、最も高い割合で検出されたにも関わらず、メタン発生量の増減に伴う存在比の変動は小さかった。メタン最発生期に存在比がピークを示したのはMethanocella属で、Methanosaeta属の存在比のピークは、メタン発生減少期であった。Thaumarchaeota門も古細菌rDNAの4割を占め、そのおよそ半分を占めたMiscellaneous Crenarchaeotic Group (MCG)は、メタン最発生期に存在比がピークとなった。一方、MCG に次いで存在比の高いCandidatus Nitrosotalea属は、土壌が嫌気的になると顕著にその割合が減少し、落水すると増大した。
keywords:水田土壌,メタンフラックス,古細菌相,16S rDNA