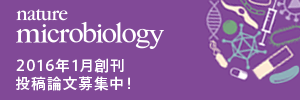PG-096:II型糖尿病を誘起する新規Lachnospiraceae科腸内細菌の系統と生理機能の解析
1国立研究開発法人 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門, 2味の素株式会社 フロンティア研究所 先端微生物機能研究グループ
近年、腸内フローラとヒトの健康や疾患との関連性が議論され始めており、特に、現代人に身近な糖尿病等の成人病は腸内フローラにより誘起されている可能性が示唆されている。特に、昨今の腸内メタゲノム解析により、腸内フローラの主要構成種であるLachnospiraceae科に属する細菌群の増加がII型糖尿病の発症と正の相関を示すことから、本科の細菌種が糖尿病の発症に関与している可能性が示唆されている。しかしながら、Lachnospiraceae科腸内細菌の多くが未知・未培養であるためその直接的な因果関係はこれまで不明であった。近年、亀山らにより高血糖性肥満マウスから新規Lachnospiraceae科細菌AJ110941株が分離され、同株を無菌マウスの腸内に定着させると、マウスの糖尿病発症が顕著に誘導されることが明らかとなった。そこで本研究では、本株の系統分類学的諸性質の解析を行った。
AJ110941株は糖類やYeast extract、ペプトン等を基質として従属栄養的に生育するグラム陽性の偏性嫌気性細菌であった。また、本細菌株はGAM培地で良好に生育し、茶色の円盤型コロニーを形成した。次に化学分類指標を同定した結果、GC含量は41.1%、主要キノンはMK-5(H4)、主な脂肪酸組成はC18:1cis9, C16:0, C18:1trans9 or cis6であった。16S rRNA遺伝子に基づく分子系統解析から同株は確かにLachnospiraceae科に属するが、本分類群に属するいずれの既知種とも相同性が92.5%以下と低く、分子系統学的に大きく異なることが明らかとなった。本株はグルコースを基質とした場合の発酵産物として酢酸を生産することや、主要な脂肪酸組成など上記のグループと類似性を示す一方で、その発酵産物にフマル酸を含むことや脂肪酸含有率などを含めグループ内の近縁種と生理学的性質が異なっていた。特に、既知の類縁菌種は直径が10μm程の桿菌や球菌であるのに対して、AJ110941株は最大で直径62.5μmの巨大な紡錘形であり、形態的にも近縁種と大きく異なっていることが判明した。以上より、AJ110941株はLachnospiraceae科に属する新属新種として提案されるべきものであることが示された。
keywords:Gut microbiota,Intestinal bacterium,Type 2 diabetes,Family Lachnospiraceae,Fusiform