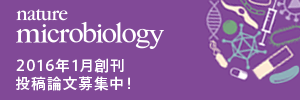PE-069:走査型透過X線顕微鏡による微生物由来の水酸化鉄(BIOS)に含まれる微生物の観察
1広島大学, 2海洋研究開発機構, 3高エネルギー加速器研究機構, 4東京大学
地球表層には鉄マットが幅広く存在しており、その多くが微生物活動により生成された水酸化鉄(BIOS)である。BIOSの形成には微細物活動を伴わない無機的な鉄酸化作用と、微生物による鉄酸化作用の両者が寄与している。しかし、BIOS中の微生物を一個体(シングルセル)で観察し、鉄酸化作用や鉄の挙動を議論した研究は少ない。そのため本研究では、局所領域で官能基や価数の同定が行える走査型透過X線顕微鏡 (STXM) を用いて、BIOS中の微生物をシングルセルで観察することを目的とした。
試料として広島大学校内にある「ぶどう池」からBIOS を採取した。このBIOSを厚み50 nmのSi3N4膜の上に散布・乾燥させ、Photon Factory BL-13Aにある小型のSTXM(compact STXM)で観察して炭素・酸素・鉄の化学状態や分布を調べた。
Compact STXM観察によりBIOS中から微生物と思われる個体1つを見つけ、炭素K吸収端でのX線吸収端近傍構造(XANES)から微生物であると同定した。また官能基イメージから、微生物は体外に多糖類や脂質をまとってSheath(鞘状有機物)上に存在していることがわかった。これらのことから微生物—Sheath境界域で鉄が関係する化学反応が起きているのではないかと示唆されたため、鉄L端でのXANES (Fe-XANES) と価数別イメージを取得した。Fe(II)及びFe(III)での価数別イメージから、微生物はSheathに比べて相対的にFe(II)に富むことがわかった。また微生物、微生物—Sheath境界域、SheathそれぞれでのFe-XANESは類似した特徴を示していたが、Fe(III)のピーク高で各領域のXANESを規格化すると微生物、微生物—Sheath境界域、Sheathの順にFe(II)のピーク高が減少した。この結果は、この微生物(おそらく鉄酸化菌)の細胞表面でFe(II)がFe(III)へと酸化されるプロセスを直接観察している可能性が高い。
本研究ではSTXM/XANESや価数別イメージを組み合わせることで、局所領域における微生物と水酸化鉄の関係を明らかにした。今後は上記の元素以外の元素の測定を行い、BIOS中での微生物の空間分布や役割をより詳細に明らかにしていく。
keywords:鉄酸化細菌,BIOS,X線吸収微細構造(XAFS),走査型透過X線顕微鏡(STXM),鉄マット,局所領域