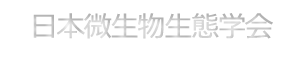微生物生態学会40巻1号 ハイライト
総説 「メタンハイドレート賦在域海底における好気・嫌気メタン酸化の共存―メタン動態と生物群集へのインパクト―」 堀 知行、太田 雄貴、宮嶋 佑典、井口 亮、塚崎 あゆみ、鈴木 淳、鈴村 昌弘、青柳 智、吉岡 秀佳 海底での好気・嫌気メタン酸化菌について、13Cトレーサー培養試験+rRNA-SIP、脂質-SIPでメタ同定することで、ANME-1とANME-2などの古細菌がそれぞれのニッチを形成して棲み分けしながら嫌気メタン酸化へ中核的に関与していること、Methylococcaceae科細菌がメタン消費に重要な役割を担っていることを発見、微生物の共存戦略が底生動物群
Posted On 16 11月 2025