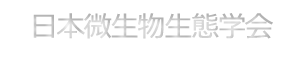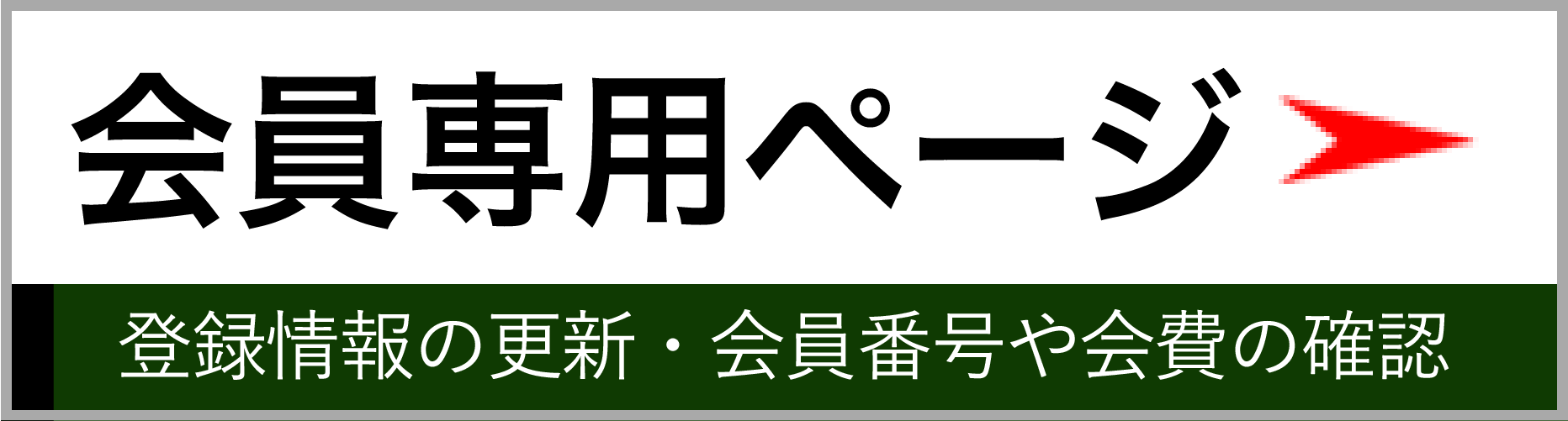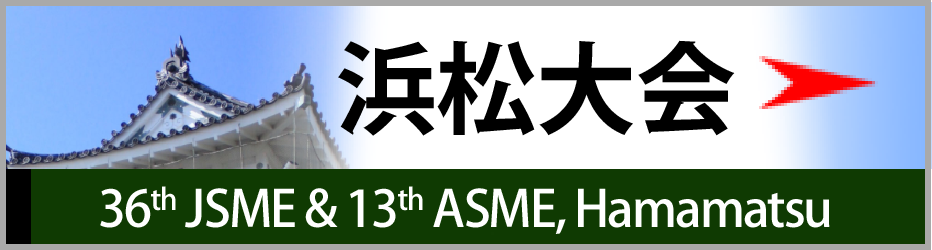2021 Microbes and Environments 論文賞選考結果のお知らせ
2021 M&E 論文賞選考委員長
高井 研
論文賞選考委員:高井研(選考委員長)、井町寛之、玉木秀幸、砂村倫成、大塚重人、豊田剛己[敬称略]
選考対象論文:2021 年に Microbes and Environments に掲載された総説等を除くオリジナル論文
論文賞受賞論文ならびに著者
Bioelectrical Methane Production with an Ammonium Oxidative Reaction under the No Organic Substance Condition
Ha T.T Dinh, Hiromi Kambara, Yoshiki Harada, Shuji Matsushita, Yoshiteru Aoi, Tomonori Kindaichi, Noriatsu Ozaki, Akiyoshi Ohashi
Microbes and Environments 36(2), ME21007 (2021)
論文賞授与理由
電気と微生物を使いCO2をメタンや単純な有機物といったエネルギー源や有用物質変換材料、あるいはバイオマスに転換する微生物電気合成システムの研究が世界的に盛んに行われている。特に、微生物電気合成システムを用いてメタン生成を実現するには0.8V程度付近 (あるいはそれ以上) の比較的高い印加電圧が必要と考えられてきた。
アノード電極反応をH2Oの酸化ではなくアンモニア酸化を利用することで、従来よりも低い印加電圧によってメタン生成を駆動させるシステムが構築できるのではないかという独創的な仮説を検証したのが本研究である。廃水処理系微生物群集を植種源として用いて、110日間にわたる微生物電気合成リアクター実験を行い、印加する電圧を変化させながら生成するメタンやアンモニア酸化に由来する窒素化合物の動態と量論を調べた。最終的に0.05Vという従来よりも遥かに低い電圧でメタン生成ができることを初めて実験的に証明した。加えて、16S rRNA遺伝子に基づいたアプリコン解析を行うことで低電圧下でのメタン生成に関わる微生物グループの特定やプロセスに迫っている。その結果として、カソード電極上でGeobacteraceaeやPorphyromonadaceaeに属するバクテリアが電子とプロトンから水素を生成し、その水素を介在してメタン生成アーキアがメタン生成を行うというモデルを提示した。電気化学的反応式を用いた理論計算から、そのモデルが論理整合的であることも検証されている。2021年M&E論文賞選考委員会の議論の中で、「本実験の植種源に使用したサンプルを説明して欲しい」、「微生物解析が実験終了時の1点ではなく時系列で見たかった」、「顕微鏡観察やオミクス解析等を行えば論文の完成度はもう少し高めることができたのではないか」、「作業仮説の独自性についてもう少し詳しい(自画自賛的な)記述があっても良かったのではないか」といった、より高みを見据えた建設的な意見が出るほど、委員の興味や共同研究者意識の高まりが見られた。本研究の著者、特に若い世代の共著者、には、ぜひ関連分野の先人達の愛のある建設的意見として参照して頂ければと思う。いずれにせよ、極めて独創的な着想に基づいた唯一無二のフルコース研究であることに全委員が深く感銘を受けた。まさにM&Eが理想とする研究論文を体現する2021年M&E論文賞(Most Valuable Paper of the Year 2021)に相応しい珠玉の1報である。
文責:2021年M&E論文賞選考委員会(高井研、井町寛之、玉木秀幸、砂村倫成、大塚重人、豊田剛己)
つづいて惜しくも論文賞には至らなかった佳作論文2報の紹介。
Leaf Bleaching in Rice: A New Disease in Vietnam Caused by Methylobacterium indicum, Its Genomic Characterization and the Development of a Suitable Detection Technique
Khoa Lai, Ngoc Thai Nguyen, Michiko Yasuda, Khondoker M.G. Dastogeer, Atsushi Toyoda, Koichi Higashi, Ken Kurokawa, Nga Thi Thu Nguyen, Ken Komatsu, Shin Okazaki
Microbes and Environments 36(4), ME21035 (2021)
イネ。稲。コメ。米。
通説では我が国で約3000年前に中国からもたらされ九州西北部で栽培が始まったとされ、また一説には鹿児島県の土壌の化学分析の結果から、約12000年前の地層にも稲由来のプラント・オパール(稲の葉に多く含まれるケイ酸が鉱物化したもの)が見つかったと言われている。「稲=日本起源説キタコレ」と言いたくなるようなやや眉唾な話、ワタクシ大好物。「蒸し御飯(645年)炊いて祝った」と暗記した大化の改新では、班田収受の法が定められ、国有財産として田んぼを与えられた人民が税として収穫物としての米を収める「コメ国家」の基盤が誕生した。以降1873年(明治6年)に行われた「地租改正」で税の主体が米から貨幣に変わるまで1200年以上の間、日本という国家基盤と人々の生活は稲(米)とあったと言っても過言ではない。
漁労民的研究者(海洋を主戦場とする研究者)であるワタクシが、知ったかぶりをして、「日本と日本人にとって米は特別なんじゃあああ」と稲作信仰と右翼っぽい事を青筋立てて力説しなくとも、米は小麦・トウモロコシと並んでぶっちぎりの世界3大穀物の一つであり、世界の人々の食糧や畜産業を支える最重要作物の一つであることは広く知られる。さらに近年では、比較的カーボンフットプリントが大きな穀物として、あるいは稲作圏の広がりとともに強力な温室効果ガスであるメタン放出量の増加が懸念されるなど、地球環境変動との関わりの観点からも注目されている。
前置きが長くなった。そんなある意味地球を代表する植物=稲に新しい病気が発生した。2010年ベトナムのことである。「ベトナム稲葉脱色病」(今テキトーに病名を作ってしまった)。被害額や将来にわたる懸念については論文では触れられていない。だが、米を偏愛してやまないワタクシからすれば地球レベルの一大事のように感じてしまう。ベトナム稲葉脱色病の状況を知った本論文の著者達は、以前の研究を通じて似たような病変を有した稲を見たことがあった。そしてそれがMethylobacterium spp.の仕業であることも知っていたのだ。セレンディピティ?必然?著者達はベトナムの稲を救うために立ち上がった(かどうかは完全にワタクシの妄想である)。ベトナムに調査に赴き、またたく間に「ベトナム稲葉脱色病」の原因微生物候補を分離し、Methylobacterium indicumが病原微生物であることを突き止めた。カッケー!「ロベルト・コッホ」「北里柴三郎」「野口英世」。思わずそんな微生物学の英雄達の名前が脳裏に浮かぶような、微生物学者として最もエキサイティングな研究の一つといえる、「病原微生物の分離と病原性の特定」に著者達は成功した。その後速やかにゲノム配列を決めたのだが既知の植物病に関わる病原遺伝子やメカニズムについては分からなかった(研究の楽しみは続くが、治療法の確立に至る道筋が作れなかった点ではヒーローにはなりきれなかったかもしれない)。それについては落胆はしたが(ここらへんもワタクシの勝手な妄想である)、LAMP法による「ベトナム稲葉脱色病」の迅速かつ簡便な原因微生物検出法を構築してしまった。そしてクールにM&Eに論文を投稿・出版した。やはりカッケー!カッケーよ!
その微生物学の覇王道を邁進するかのような本論文に、2021年M&E論文賞選考員会の1次選考過程での議論は盛り上がった。特に関連分野にやや疎い漁労民的研究者であるワタクシは、鼻息荒く「MVPはこの論文以外あり得ない!」と強弁したものだ。しかし最終選考過程での議論では、「植物の病原微生物の分離と特定の研究例は結構あって、やはり病原性メカニズムの理解への展開が欲しいところである」という客観的な観点からの意見もあった。「愛する米の救世主爆誕」にバカみたいに興奮していたワタクシはやや意気消沈した冷静さを取り戻した。
少し専門が違うと評価はとても難しい。
芥川賞もレコード大賞もアカデミー賞もノーベル賞もそういうものかね。
2021年のM&E誌に掲載された40報の論文の中で一番心が揺さぶられた論文はどれだ?その結論を出す最終選考過程はそれぞれの委員の価値観がぶつかり合う、激しくも楽しい場となった。その議論の結末として、M&E MVP of The Year 2021=Dinh et al., Microbes and Environments 36(2), ME21007 (2021)が決定し、再び世界に平和が訪れた。
微生物学研究の価値やインパクトは研究の(技術的)難易度や社会的な影響力で決まるわけではない。本論文は、いい歳したヨレヨレ微生物ハンターをワクワクさせる微生物学の本質的な魅力が詰まっている。そこに微生物が引き起こす現象があるなら、微生物学者は世界の果てまで行ってでも、火星や土星の衛星に行ってでも、誰よりも先にその原因の微生物を分離したいのだ。そんな微生物学研究者の業と真髄を本論文は体現している。諸君、本論文を一読すべし!
文責:2021年M&E論文賞選考委員会委員長 高井研
Imbalance in Carbon and Nitrogen Metabolism in Comamonas testosteroni R2 Is Caused by Negative Feedback and Rescued by L-arginine
Abd Rahman Jabir Mohd Din, Kenshi Suzuki, Masahiro Honjo, Koki Amano, Tomoka Nishimura, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Hidehiro Ishizawa, Motohiko Kimura, Yosuke Tashiro, Hiroyuki Futamata
Microbes and Environments 36(4), ME21050 (2021)
著者のグループは、先行研究において、「Comamonas testosteroni R2株が、フェノールを単一炭素・エネルギー源とする好気性バッチ培養(回分培養)条件では増殖し完全分解するものの、フェノールを単一炭素源とするケモスタット培養(連続培養)条件では培養系が崩壊(collapse)する」という極めて興味深い現象を発見した。というのも、回分培養では増殖に伴い排出される代謝産物等の影響により活性が低下することが一般的で、高い活性を安定して維持するために開発されたのが連続培養だからである。
本論文では、連続培養条件下でのR2株の培養系崩壊と、フェノールを単一炭素源とする回分培養条件下での好気的増殖について、生理学的手法およびトランスクリプトーム解析を用いて検討している。
この研究により、連続培養系ではR2株のフェノール/カテコール分解活性は徐々に低下し、分解活性がある閾値を下回ると(分解活性は残っているものの)、フェノール蓄積が生じ、増殖が阻害されて結果的に培養系が崩壊することが示された。生理学的解析の結果、安定してフェノールが分解される条件下で始まったフィードバック成長阻害により、この崩壊が誘導されることが分かった。トランスクリプトーム解析の結果からは、一次代謝の活性が安定状態の約60~70%に低下していた。さらに、培養系崩壊時には窒素輸送関連遺伝子の発現が上昇しており、細胞内のNH4+濃度の増加と炭素骨格の供給量の減少に基づく炭素代謝と窒素代謝のバランス崩壊が、R2株の崩壊を引き起こしたと考えられた。また、培養系崩壊の状態でR2株は尿素サイクルが抑制されていた。
ところが著者らは、培養系が崩壊したR2株に、尿素サイクルのアミノ酸(L-アルギニン、L-オルニチン、L-シトルリン)、L-グルタミン酸、L-グルタミンを与える試験を行い、唯一L-アルギニンだけが、細胞増殖に利用されず、R2株を崩壊から救済(rescue)する作用を持つことを発見した。つまり、他のアミノ酸は崩壊時においても同化過程に回されるにもかかわらず、L-アルギニンは同化には利用されず、抑制されていた尿素サイクルを促進するトリガーとして機能することを明らかにした。
本論文は、このように緻密な実験とバイオインフォマティクスを組み合わせてR2株の崩壊過程を詳細に解析したものであり、非常に丁寧な考察を行っている。行った実験はR2株という単一の培養株を用いたものであるが、イントロダクション、実験設定、議論の内容などから、その先には微生物群集機能の安定性や代謝ネットワークにおける種間相互作用への著者らの興味がはっきりと見える。本論文により、「R2株を崩壊から救う方法を開発する」という著者らの目的は果たされている。しかし研究はここで終わりではないだろう。L-アルギニンによる崩壊からの救済という新たな現象の発見が、次なる研究の幕開けを予感させる。また、窒素が様々な細菌の一次代謝や二次代謝を調節していることを考えれば、細菌が細胞内のNH4+濃度をどのように調節するのかということも、著者らの今後の研究の鍵の一つとなりそうだ。
文責:2021年M&E論文賞選考委員会委員 大塚重人、豊田剛己
最後に2021年M&E論文賞選考委員会委員がどうしても紹介したかった推し論文
Optimized Cultivation and Syntrophic Relationship of Anaerobic Benzene-Degrading Enrichment Cultures under Methanogenic Conditions
Hop V. Phan, Futoshi Kurisu, Koichiro Kiba, Hiroaki Furumai
Microbes and Environments 36(3), ME21028 (2021)
本論文は,未だ不明な点の多い「無酸素環境下におけるベンゼン分解メタン生成」に関与する中核的微生物とその周辺微生物の役割の一端を明らかにしたものである。具体的には、著者らが長年かけて育んできたベンゼン分解メタン生成集積培養系を活用し、通常は遅いベンゼン分解の速度を高め、誘導期を短縮するような最適な培地組成を見出すとともに、確定した新しい培地を用いることで、ベンゼン分解に関与するとみられるDeltaproteobacteriaの未培養系統群Hasuda Aの増殖を促進し、より集積できることを明らかにしている。さらに興味深いことに、新しい培地を用いると、Hasuda Aに加えて、3種のメタン生成アーキアおよびOD1(候補門Ca. Parcubacteria)に属する細菌種が増殖促進され、Hasuda Aと共に集積培養されることを見出している。さらに、培地組成の検討で見出した「ベンゼン分解が阻害される条件」においてはOD1の個体群が減少することもあわせて見出しており、OD1の個体群は、Hasuda A、メタン菌とともにベンゼン分解メタン生成と正の相関にあることを示唆する結果を提示している。
本論文の特筆すべき点は、培地組成の再考と最適化という地味であるものの重要な検討を行うことで一般的に「遅く、不安定」とされているベンゼン分解メタン生成反応を促進し、誘導期を短縮できることを実証したことに加え、未培養ベンゼン分解菌とメタン生成アーキアとともに、未だ未培養で謎の多いOD1細菌の増殖促進現象を見出したことである。このことは、OD1細菌が未培養ベンゼン分解菌Hasuda Aもしくはメタン生成アーキアに寄生・感染しうる可能性を示唆するものであり、今後、無酸素環境下におけるベンゼン分解メタン生成のメカニズム解明ならびにOD1細菌の役割の解明に繋がる重要な基盤的知見を提示している成果として高く評価できる。今後のさらなる調査が期待される。
文責:2021年M&E論文賞選考委員会委員 井町寛之、玉木秀幸
A Novel Archaeal Lineage in Boiling Hot Springs around Oyasukyo Gorge (Akita, Japan)
Katsuhiro Asamatsu, Kai Yoshitake, Makoto Saito, Wipoo Prasitwuttisak, Jun-ichiro Ishibashi, Akihi Tsutsumi, Nurul Asyifah Mustapha, Toshinari Maeda, Katsunori Yanagawa
Microbes and Environments 36(4), ME21048 (2021)
本論文は、秋田の温泉水の微生物群集構造解析を実施し、新門相当の配列を発見した報告である。メタ16S rRNA(SSU rRNA)遺伝子解析を通じて分類できないArchaea OTUsが一定数存在することに着目し、より長いSSU rRNA遺伝子配列を獲得しつつキメラ等の可能性を排除するために、他の複数のプライマーセットを試し、一つのプライマーセットから同じOYSグループと名づけた新規の配列が得られることを示した。
前世紀(20世紀)後半、環境中のSSU rRNA遺伝子配列を用いた未知の微生物の発見が相次いだ時代から30年近くが経ち、多くの調査や研究によってデータが蓄積されてきた。その後、3大rRNA遺伝子配列データベースの一つであるGreengenesデータベースは10年前から更新が止まっているにも関わらず、多くの研究で現在も利用されている。このことはSSU rRNA遺伝子配列から新しい分類群が見つかることはほぼ無くなってきている現状を意味する。言い換えれば、あらゆる環境において環境SSU rRNA遺伝子解析はほぼやり尽くされたと言える。
ましてや、温泉や海底熱水を対象とする環境SSU rRNA遺伝子解析研究は初期の頃からのメジャー対象環境であり、まさにオワコンともいえる環境。最近になっても、生物地理・経時変動・環境モニタリング等の調査が行われており、どこかで見たような配列ばかり。このような背景の中、環境SSU rRNA解析全盛の時代を生きてきた我々(砂村と高井)は、著者らが日本の温泉環境で相対頻度5-13%を占める新門相当のOYSグループの配列を発見したことに驚いた。例えるなら「失われた古の武器で狩りに出陣しドラゴンを狩ってしまった」。ここからは我々の勝手な想像に過ぎないが、昨今のシーケンス技術の劇的な進歩と得られる膨大な配列処理の過程で、解析がパイプラインで行われ、データ自体はブラックボックス化し、必要なデータをいかに効率よく残すかが重要になってきている中で、あえてこの未分類Archaeaに着目してさらに解析したことが功を奏したのではないだろうか。人海戦術・物量作戦的研究ができない境遇だからこそ(と勝手に想像するが)、得られたデータを精査し、それを十二分に活かそうとした著者達の努力と、そして頑張っている研究者に時々笑顔を見せてくれる微生物学の女神からの幸運が、この発見につながっているのだと思う。
今後、YSS系統のMAG作成に基づく機能推定やリボゾームタンパク配列を用いた分類、FISHによる細胞の存在形態や存在量の解明、生物地理と進化の関連といった展開を期待する。
なお我々は、本論文を論文賞候補ではなく個人推しの論文として、ここに紹介記事を書いている。そこに込められた我々の想いを最後に記したい。極限環境微生物研究は、人間や社会活動に近い土壌や農地、廃水処理や水圏といった環境を扱う研究とは違い、環境へのアクセスが極めて難しく、試料採取や分析・実験が(物理的および金銭的に)難しい研究対象である。そのため、論文としての完成度や完結性が低くなりがちで、論文の査読でも査読者から「アレが足りないコレが足りない」とツッコミ所満載の場合も多い。実験室内で実環境条件を再現し、実験系でデータ解釈を検証するのもさらに困難である。それでも人類がまだ見たことのない風景、研究者がまだ訪れたことのない環境、あるいは手にしていないような試料、を目の前にすれば、「まずは物理・化学環境分析とSSU rRNA遺伝子解析してもろて」と、未知の微生物の存在と発見への期待に心震わせるのである。もちろんそれは、未知の系統や分類群という意味だけではない、さらなる研究の先にある未知の代謝や生理・生態機能かもしれないのだ。
文責:2021年M&E論文賞選考委員会委員 砂村倫成、高井研