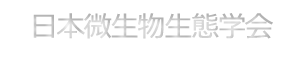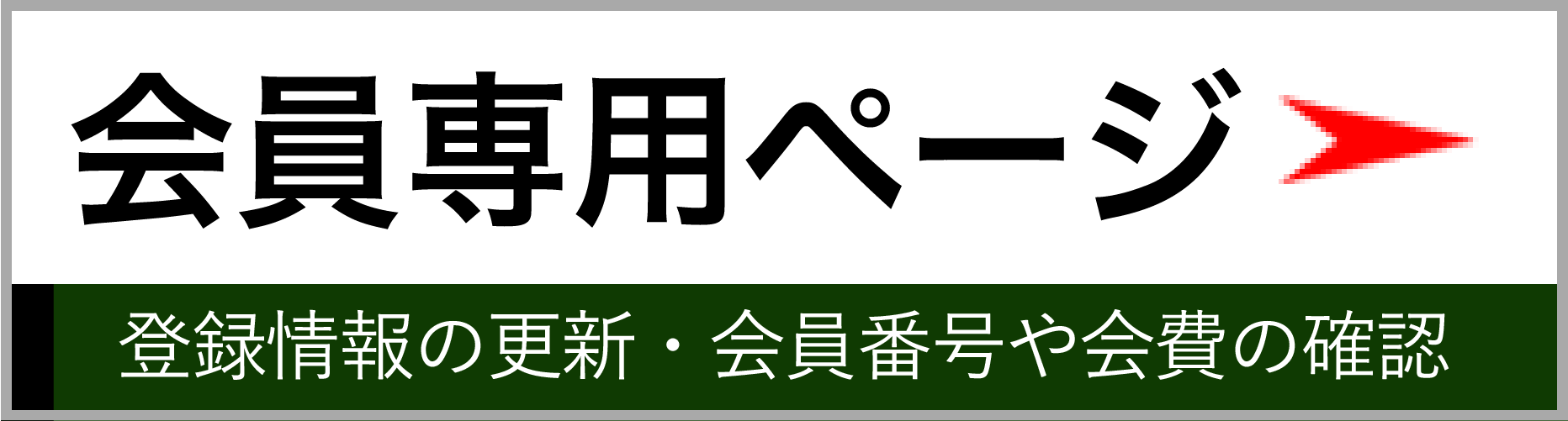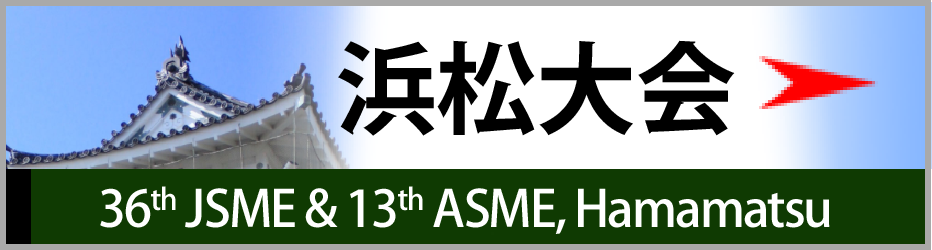微生物生態学会 31巻2号 ハイライト
総説
抗菌薬剤感受性試験結果に基づく銅イオン溶液の抗菌・殺菌作用過程 石田 恒雄
金属イオンと金属錯体は,生体系物質のアミノ酸,タンパク質,酵素などとの生体分子との相互作用,環境中に排出する病原性微生物の生態と制御,医薬への応用や病原菌や疫病との関係についての関心が近年急速に高まってきている。銅イオンは,抗菌,防汚剤や殺菌剤などに広く利用されているが,銅イオンと銅錯体は抗菌・抗ウイルスに対してより高い有効薬剤として発現されることが予想される。本稿では,グラム陰性菌あるいはグラム陽性菌に対する表層構造である細胞壁,細胞質膜,細胞質の各過程における銅(II)イオンの移動,反応,透過に伴う抗菌・殺菌作用を溶菌機序と金属錯体形成論から解析・考察し,明らかにした銅(II)イオンによる抗菌作用機構について紹介する。
氷河・積雪上の微生物の生態 瀬川 高弘,竹内 望
グリーンランドをはじめとする北極圏を中心に,雪氷上に繁殖する「雪氷微生物」に各国研究者の関心が近年高まっている。その理由は,地球温暖化に伴い北極の雪氷環境が急激に変化していること,予想を上回る近年の雪氷の融解量にこの雪氷微生物が関与していると考えられることである。さらに,氷河や氷床の後退や雪氷微生物の存在は,北極に限ったことではなく,全世界の雪氷圏に共通している。今まで生物学的にほとんど注目されることがなかった雪氷圏が,一つのバイオームとして認知されるようになった。雪氷上で繁殖する好冷性または耐冷性の雪氷微生物は,氷河の表面に現れる雪氷藻類とよばれる光合成微生物,そしてその生産物に依存した従属栄養性細菌などで構成される。本稿では,雪氷微生物とはどのような微生物なのか,最近報告されている論文を中心に紹介する。
リサーチ最前線
排水処理生物反応槽におけるN2O を還元可能な細菌群の利用可能性 寺田 昭彦,末永 俊和
亜酸化窒素(N2O)は二酸化炭素の約300倍の温室効果を示すことに加え,フロンに替わるオゾン層の破壊に寄与する21世紀最大の原因物質として知られている。N2O削減に寄与する脱窒細菌や,N2O還元以外の脱窒酵素を保有しない偏性的なN2O還元細菌の生理・生態は,排水処理施設をサイトとした研究はあまり進んでいないが,排水処理施設からのN2O放出量削減の必要性が論じられてきている。本本稿では,このN2O削減の解決策になりうる,N2O還元細菌の重要性とN2O 還元細菌の活性を維持可能な環境を模擬するバイオフィルムリアクターについて紹介する。
扉を拓く – 活躍する若手
新たな分離培養技術が照らす未来~硝化菌の獲得から学んだこと~ 藤谷拓嗣(早稲田大学)
2015年のコマモックスの発見は大きな注目を集めています。今回は,未培養の硝化菌の分離培養に挑戦し続けておられる,早稲田大学の藤谷先生にお話を伺いました。
放射光を使った微生物研究―これまでの研究を振り返って― 光延 聖(愛媛大学)
放射光源X線顕微鏡をメインツールとして,海底下の岩石圏と陸上の土壌圏での微生物-鉱物-元素相互作用について研究している愛媛大学の光延聖先生にお話を伺いました。