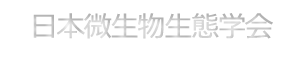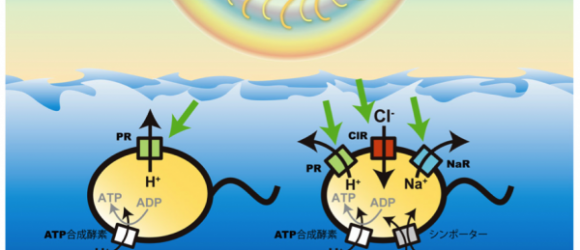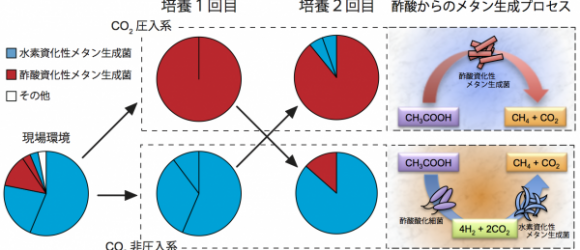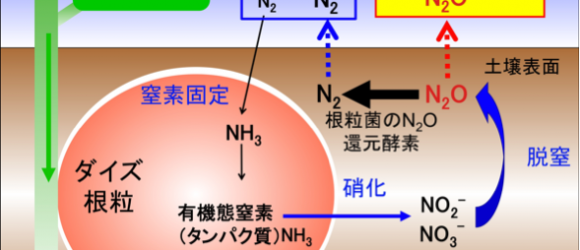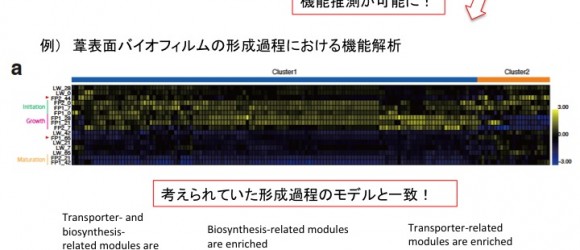Web掲載用情報提供のお願い
微生物生態学会webでは、 ・トップページの画像 ・学会員の受賞やプレスリリース の情報を求めています。 情報の送付先は、微生物生態学会事務局(office[at]microbial-ecology.jp)です。メール添付でお願いします。([at]は@マークで置き換えてください) 掲載する情報 1.トップページ画像:微生物生態学に関する画像。顕微鏡写真、対象環境など。画像はjpeg画像(500 x 300 ピクセル推奨)としてお送りください。画像の加工については、広報担当でも対応します。 2.プレスリリース等:Nature姉妹紙などに掲
Posted On 08 5月 2014