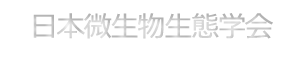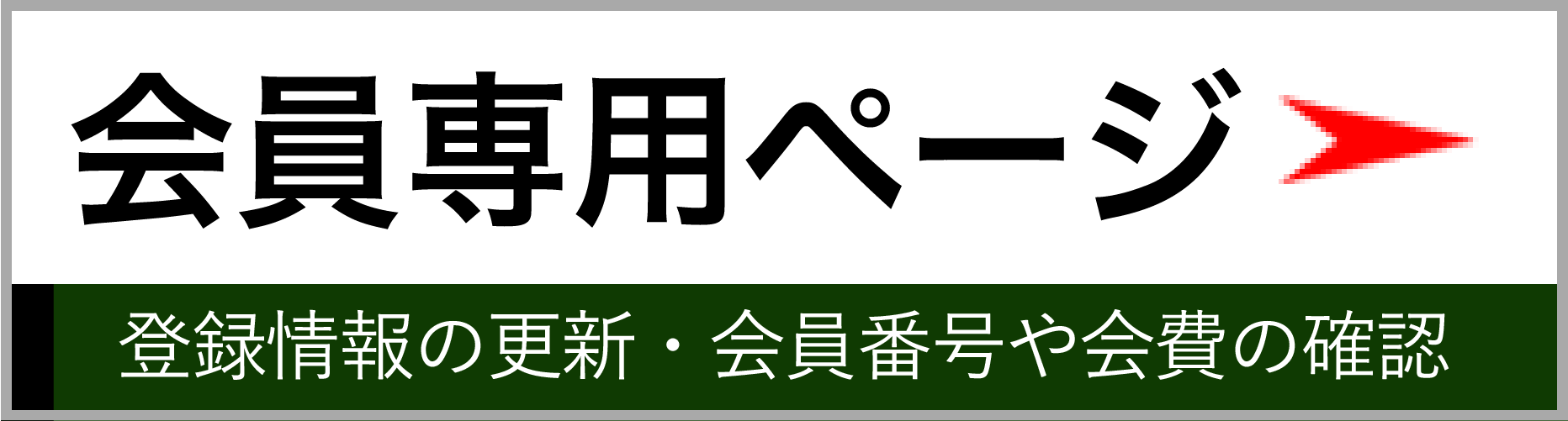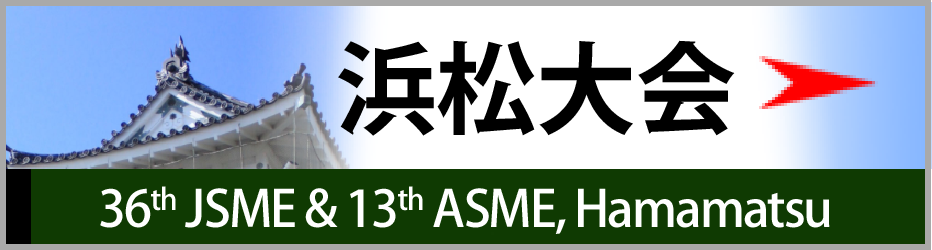ISME SeqCode ならびにICSP対応WGの設置と参加者募集について
日本微生物生態学会会員の皆様へ
日本微生物生態学会会員は、International Society for Microbial Ecology (ISME)創設以前より、ISMEコミュニティーへ大きく貢献し、京都にて開催されたISME 6では1000人を越える参加者がありました(諏訪氏執筆記事をご覧下さい:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmeja/31/1/31_KJ00010256760/_pdf/-char/ja)。しかし、現在では、ISME大会への参加者数は減少し、運営への貢献も薄れ(ボードメンバーはおらず、Ambassador浜崎氏、岡部氏、Young Ambassador 青井氏)、更にジャーナル編集への貢献も低下しています(ISME J: SE 1名, EB3名、ISME Communications: EB1名)。
このような状況において、近年、ISMEが主体となる微生物のゲノム配列を基準とする新たな分類体系(SeqCode Initiative)が発足し、ICNP(International Code of Nomenclature of Prokaryotes)による分類体系と並列、部分的には対立する極めて複雑な状況が生じています。現在、この問題はICNPに関して責任を持つICSP (International Committee on Systematics of Prokaryotes)(ICSPにはSeqCode推進派[正確には、ゲノムを基準とした分類体系を推進する]委員も含まれています)、Bergey’s Society、IJSEM誌上等々で議論が行われていますが、どのように収束するのか全く見通せない状況です。その一方、日本の微生物学ソサエティーにおいては、ICSP Executive Boardには2023年から1名の委員(理研・JCM 坂本氏)が参画しているものの、SeqCodeに関しては発足のきっかけとなったゲノムを基準とする分類体系提案やその後の否決に至るまでの議論において、日本からの研究者の関与は極めて限られており(当時、ICSP Executive Boardにおいては欠員状態でした)、実質的に決定後の公開情報のみに触れるのみ、という状況でした。また、ICSPでの提案否決前後からSeqCode発足に至るまで、数回のISME 大会におけるラウンドテーブルセッション等での議論、ICSP、Bergey’s trust関連の会合等を経てはいるものの、それらへの日本研究者の貢献も限られていました。そして、それらの枠組み外で開催されたワークショップ等、欧米豪の研究者ネットワーク主体での議論においてもその存在は希薄なものでした。実際、ゲノム配列を基準とする分類体系の提案論文(Murray et al. 2020)の査読過程において実施された個人的ネットワークによる国際的な意見聴取の対象となった日本の機関に所属する研究者は、公開情報からは2名に限られ、また、以降の様々な意見を交わす論文においても著者として加わっている日本の機関に所属する研究者は知る限りおりません。更に、ISMEのSeqCode Initiative自体、有志による組織構成であり、SeqCodeに関する情報が公開情報に限られる研究者にとっては参画の敷居が高い現状があります。なお、ICSPは国際微生物学連合(IUMS)傘下にあり、日本国内からのアクセスは、微生物学連盟(実質的には微生物資源学会)経由で、確保されています。
日本の研究機関から発表される単離微生物の新種記載の数は、中国やインド等次ぐものであり、また、高次レベルで新規な菌株を単離し、記載する研究者も多く存在します。現実に、ICNPとSeqCodeに挟まれ、論文発表や査読の場で苦労される状況も存在します。さらに最近になって、ICSPがIJSEMで発表した「The best of both worlds」では、ICSP側からSeqCode側への配慮とも捉えられる規則の改訂が提案されており(Arahal et al., IJSEM 74:006188)、日本国内においてもICNPとSeqCodeの両面から原核生物の命名に関する理解を深めるための議論をすべき時期であると考えられます。
これらの状況を踏まえSeqCodeに対する国内微生物ソサエティからのアクセスを確保し、詳細な情報を収集する体制を整える必要があります。上記の通り、これまではSeqCodeは勿論、それを支えるISMEへの明確な国内対応組織は存在しませんでしたが、歴史的経緯を鑑み、日本微生物生態学会がSeqCodeに対する微生物生態学会員への、そして、国内微生物ソサエティーへの窓口として機能するべく、本WGを設置することとしました。SeqCode Initiativeは有志による組織体系ではありますが、日本国内の諸般の状況を考慮し、本WGの活動を通して、SeqCodeやその他の微生物分類に関する国際活動に参画する会員を支援します。また、本WG活動を通し、関連情報の国内微生物ソサエティーへの情報展開を積極的に行ないます。そして、一連の活動を通し、学会員・国内微生物ソサエティーが確定した国際ルールを受動的に受け入れるのではなく、主体的な情報発信を行うことで、よりよいルール作成・改正に向けた基盤の構築をWGの活動を通して目指します。
発足準備にあたり、下記の世話人及び委員の参画を内諾いただいておりますが、WGの発足にあたり、改めて、広範な分野の会員の皆様からのWG参画を期待しております。当WGへのご参加を希望の方は、2025年2月28日(金)を目処に、学会事務局(office[at]microbial-ecology.jp)宛に、お名前とご所属情報を添えてご連絡ください。
日本微生物生態学会事務局
———————————–
WGの役割
・SeqCodeとICNPの現状に対する情報収集
・SeqCodeの状況及び課題等について学会員と国内微生物ソサエティーへの紹介
・SeqCode Initiativeへの関与または参画についての検討
・日本微生物生態学会員あるいは国内微生物ソサエティーからのSeqCodeの運営やルール、さらにICSPの今後に対する意見表明
WG委員
世話人
布浦 拓郎(JAMSTEC)
大熊 盛也(理研JCM)
玉木 秀幸(産総研)
高井 研(JAMSTEC)
鎌形 洋一(産総研)
成廣 隆(産総研)
黒田 恭平(産総研)
伊藤 英臣(産総研)
井町 寛之(JAMSTEC)
Masaru K. Nobu (JAMSTEC)
中島 悠(JAMSTEC)
坂本 光央(理研JCM)
西原 亜理沙(理研JCM)
森 浩二(NITE NBRC)
玉澤 聡(NITE NBRC)
岡嵜 友輔 (京都大学)
———————————–
SeqCode Initiative 発足以前・以後の議論の流れ
2010: ゲノム配列に基づくDigital DNA-DNA hybridizationの導入
2016: 遺伝子配列(ゲノム)に基づく分類体系の提案
2019: Round table discussion (ISME 17)
2019: ワークショップ開催 (NSF支援)
2020: Murray et al. Roadmap for naming uncultivated Archaea and Bacteria (Nat Microbiol) 査読中に個人ネットワークに基づく国際的な意見聴取
2020: ICSPによる2016提案の否決 (Sutcliff et al. IJSEM)
2021: Web 国際ワークショップの開催
2021: 42門を定義(Oren and Garrity IJSEM)
2022:Hedlund et al. (Nat Microbiol): SeqCode発足を表明する2021国際ワークショップレポート
2022: SeqCodeによる分類体系を紹介(Whitman et al. 2022 Syst Appl Microbiol)
2022: SeqCode Initiativeの開始
2022: Goker et al (IJSEM) SeqCodeに対するICNPの立場表明
2023: Oren & Goker(IJSEM)Candidatus 門の名称に関する整理
2023: Oren (Can. J. Microbiol) 21世紀における微生物命名について
2023: Groker & Oren (IJSEM) kingdom及びdomainの分類体系への導入提案
2023: Groker (IJSEM) 欠落していたclass, order, familyレベルの名称を記載
2023: 4門を追加定義(Oren and Garrity IJSEM)
2023: Rossello-Mora et al. (System Appl Microbiol)System Appl Microbiol誌におけるICNPとSeqCodeへの考え方を取りまとめ
2023: Syst Appl Microbiol誌がICNPとSeqCodeを両立させる投稿規定を導入
2023: Whitman et al. (ISME Commun) SeqCodeとCandidatus nameの関係性についての議論
2024: Arahal et al. (IJSEM) SeqCodeとICNPの共存の為のCandidatus nameに関する明確なルールの提案
2024: Whitman et al. (mLife) SeqCodeの紹介
2024: Sutcliffe et al. (System Appl Microbiol)SeqCodeへの参画の呼びかけ
2024: Arahal et al. への反対意見表明(Whitman & Venter, System Appl Microbiol)
2024: Jimenez & Rosado (ISME J) SeqCodeの成り立ち・仕組み等に対する第三者的評価
2024: Lata et al. (Indian J Microbiol) SeqCodeの紹介
2024: Venter et al. (System Appl Microbiol)SeqCode利用の紹介
その他、Bergey’s Trustでのセミナーを通した議論は、以下より視聴可能
https://bismis.net/bismislive.html
https://www.youtube.com/@BISMiS_