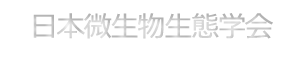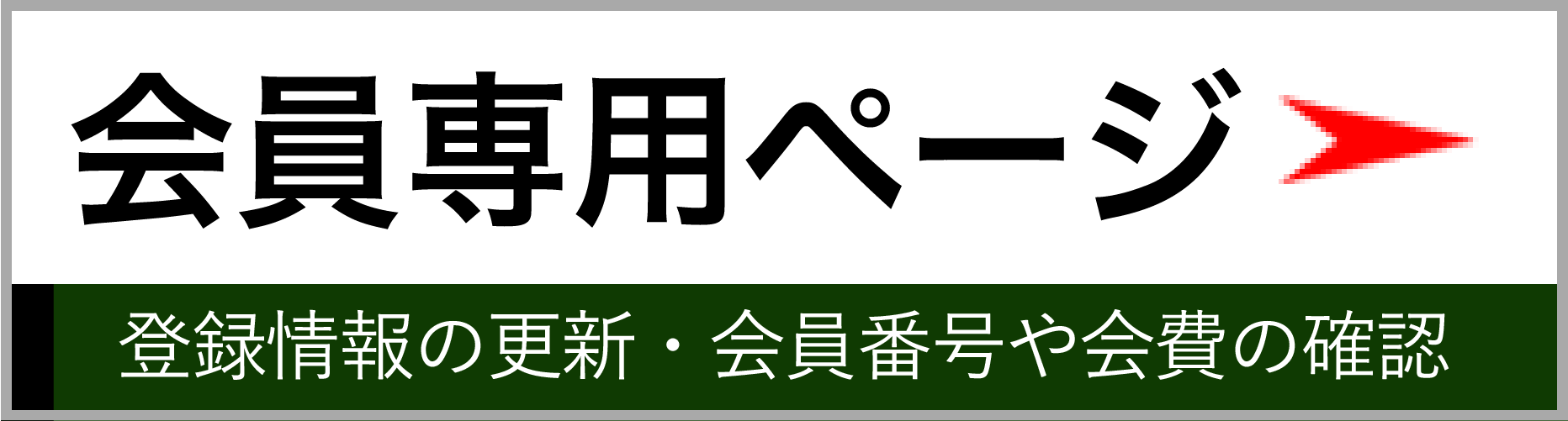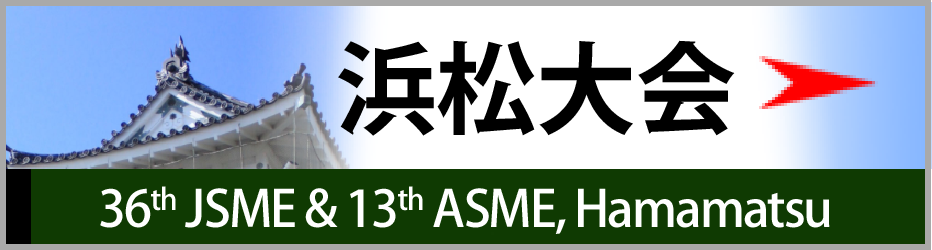微生物生態学会40巻1号 ハイライト
総説
「メタンハイドレート賦在域海底における好気・嫌気メタン酸化の共存―メタン動態と生物群集へのインパクト―」
堀 知行、太田 雄貴、宮嶋 佑典、井口 亮、塚崎 あゆみ、鈴木 淳、鈴村 昌弘、青柳 智、吉岡 秀佳
海底での好気・嫌気メタン酸化菌について、13Cトレーサー培養試験+rRNA-SIP、脂質-SIPでメタ同定することで、ANME-1とANME-2などの古細菌がそれぞれのニッチを形成して棲み分けしながら嫌気メタン酸化へ中核的に関与していること、Methylococcaceae科細菌がメタン消費に重要な役割を担っていることを発見、微生物の共存戦略が底生動物群集にまで影響することも明らかにした研究事例について紹介している。
「深海氷層堆積物の微生物生態学研究」
小林 香苗、平岡 聡史、野牧 秀隆
深海堆積物微生物叢に関する包括的な総説として、環境特性からサンプリング手法、微生物の分離培養・シーケンス解析、化学勾配解析、窒素循環への寄与まで体系的に紹介されている。深海底は海洋底の9割以上を占める広大な環境でありながら、観測・調査が容易ではない環境であり、その場の理解、ひいては全球規模での物質循環への寄与の解明につなげていくには、微生物学・地球化学・モデリングなどにまたがる学際的なアプローチの必要性を強調している。
「マイコプラズマ属名変更の論争」
柿澤 茂行、水谷 雅希
マイコプラズマおよびその類縁細菌について新たな学名が提案され、新名称の意義や名称変更に伴う問題点について専門家間で意見が対立している現状を分かりやすく概説している。現在でも議論が続いて明確な決着には至っていないが、日本マイコプラズマ学会学術集会では「和名・属名ともにマイコプラズマ(Mycoplasma)を使い続けても問題ない」との見解を示している。ICSP Mollicutes Taxonomy班や国際マイコプラズマ学会でも継続的に議論が行われており、今後の動向が注目される。
世代を超えて
「10代の人間はなにを求めているのか?」
鈴木 聡
ここ数年、高校生を対象に進学や大学についての講演をしている鈴木先生。その経験を通じて、将来に不安を抱く学生が一定数存在することを実感している。特に興味深いのは、現代の10代には「妄想」すらしたことがない学生が増えているのではないかという指摘である。肉体的には自然に成長を遂げる10代であるが、真の意味での「頭脳大人」になるためには、まず彼らに”思い浮かべる”行為そのものを教える必要があると著者は考えている。そして、10代の若者たちが豊かな妄想と想像力を持って未来を描けるようになってほしいという願いで文章を締めくくっている。
リサーチ最前線
日本微生物生態学会第37回大会のポスター賞受賞者のコメントを掲載しています。