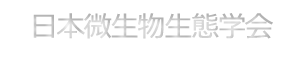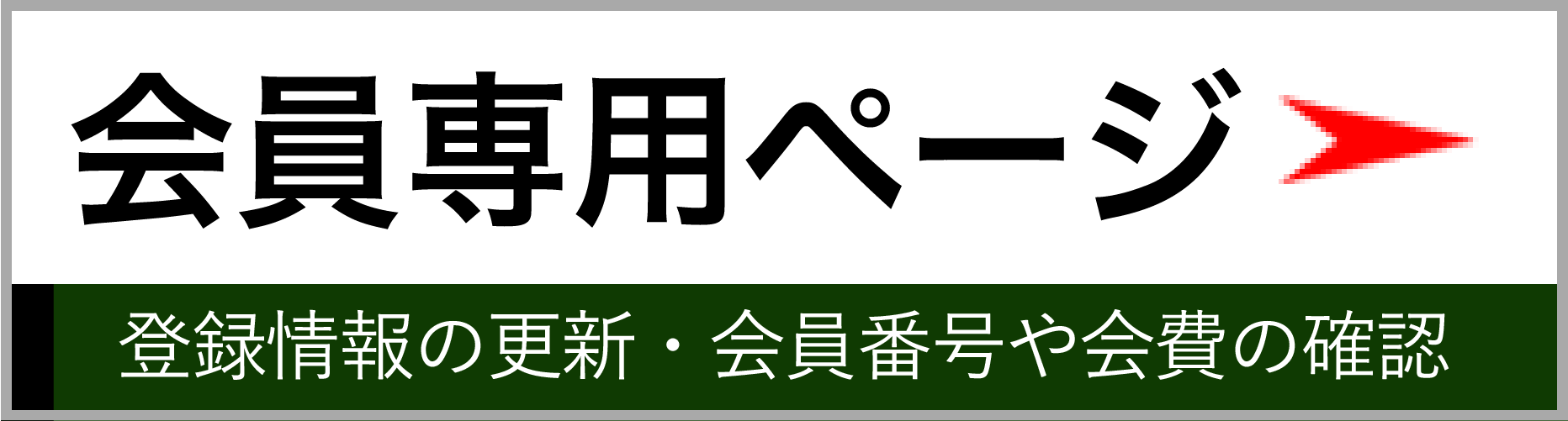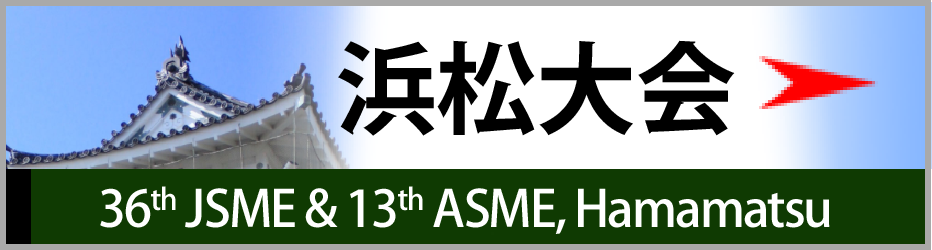吉澤晋氏
東京大学大気海洋研究所、地球表層圏変動研究センター講師
受賞理由
吉澤氏は東京大学海洋研究所(現、大気海洋研究所)にて発光細菌に関する学位論文をまとめた後、同所およびMITにて海洋微生物の新たな光エネルギー利用機構である微生物型ロドプシンに関する研究を行ってきた。ロドプシンとはレチナール色素をクロモフォアとして持つ7回膜貫通型の光受容タンパクで、光センサーあるいは光駆動型のイオンポンプが知られる。後者の場合、光を受容することで細胞内から外にプロトンを排出し、内向きのプロトン駆動力を形成してATP合成を行う。2000年にメタゲノムを通じて発見されたプロテオロドプシン(PR)はこの例にあたり、その後の遺伝子解析を通じて海洋表層の海洋細菌の半分以上がPR遺伝子を持つと推定されてきたことから、PRを通して海洋細菌が受け取る太陽光エネルギー量の見積りがその生態的な役割を明らかにする上で喫緊の課題となっていた。吉澤氏は培養条件やPR遺伝子の検出法の検討を行い、PR遺伝子を持つ海洋細菌の100株以上の分離培養に成功し、それらの株を用いて、光照射下でのプロトン排出活性の実測に成功した。これによって、PRを通じて海洋生態系に流れ込む光エネルギー量の定量的推定を初めて可能にした。さらに、遺伝子解析技術を用いて様々な細菌群が持つPR遺伝子の解析を進め、これに生化学的あるいはエネルギー論的な知見を加えてナトリウムの排出および塩化物イオンの取り込みを行う新しいロドプシンの存在を明らかにした。これらの成果はいずれも真正細菌では先行例のない独創性の高いものであり、近年Nature, Nature Communication, PNASなどに相次いで発表された。
吉澤氏のロドプシンに関する一連の研究は微生物型ロドプシンの進化的背景や生態学的役割に根本から再考を迫るものであるのみならず、生物物理学、構造生物学、さらにはオプトジェネティクスなどの生命工学分野の研究者からも注目を集めている。このように吉澤氏の研究は微生物生態学の研究課題をさらに大きな研究領域へと発展させるものであり、高く評価されるとともに今後の学際的な展開が期待される。一方、吉澤氏は学会の若手会あるいはKTJシンポジウムなどで積極的な役割を果たし、若い研究者のまとめ役としての役割も果たしてきた。
こうした微生物生態学への科学的貢献、学会への貢献、研究者としての将来性を総合的に考慮し、吉澤氏に奨励賞を送る授与することが相応しいとの結論を得た。
受賞者の声
光と微生物の関係に魅せられて
吉澤 晋
はじめに、共同研究者および支援・アドバイス・叱咤激励してくださった数多くの方々に厚く御礼申し上げます<(_ _)>。
私が初めて微生物生態学会に参加したのは22回大会(2006年)で、博士課程の1年生の時だ。修士課程までは、ナノ、ピコ秒レベルの分光測定を得意とする物理化学研究室に所属していたため、微生態の定番手法であるDGGE、FISH、16S rRNAクローンニング法でさえ、その斬新さに衝撃を受けたのを鮮明に記憶している。分子生物学的手法を用いた研究発表に多くの人が目を輝かせていた時代ではあったが、私の研究テーマは「発光細菌の“培養株”が放つ光の色の多様性を明らかにする(DNAを見ても光の色は分からない)」という夏休みの自由研究の延長のような内容であった。しかしながら、幼少の頃から光と色に興味があり、高校在学中は絵を描くことに明け暮れ、高校卒業後3年間は大学にも行かず自称絵描きをし、学部、修士課程では発光細菌の蛍光タンパク質の分光法を用いた解析、博士課程からは自ら分離した発光細菌の発光色を片っ端から調べるという研究を行うことができ、分子生物学的手法を習得できないという一抹の不安を抱えながらも、光と色に囲まれた研究生活を大いに楽しむことができた。闇雲に発光色を測定した理由であるが、発光細菌は青色か黄色を放つ種類しか知られておらず、赤色や緑色に光る発光細菌が見つかっていないのはサンプル数が足りないだけだと信じていたからだ。しかしながら、世界中の様々な海域から分離した1000株以上の発光を測定した結果、いわゆる青色の範疇に入る発光色しか確認することができなかった。ルシフェラーゼのアミノ酸に一つ変異を加えるだけで発光色が劇的に変化する事例が知られていただけに、青色にしか光らない発光細菌のストックを山のように抱え呆然とした。ただ、それと同時に青い発光色にこそ発光の生態学的意義が隠されていると考えるきっかけになったことも事実であり、微生物が生きる“多様な色を許さない秩序整然とした世界”を垣間見たことで、ますます光と微生物の関係への興味が深まった。学位取得後は、微生物の新しい光ネエルギー機構であるロドプシンの研究を開始し、素晴らしい共同研究先や数々のラッキーに恵まれ成果が出つつある段階である。
自らの研究内容を振り返ってみると、光と微生物の関係への興味、またバックグランドが物理化学ということもあり、微生物生態の定番手法にこだわることなく研究テーマを考えてきたのが一番のオリジナリティーだと思うが、それに気がついたのはつい最近である。微生物生態の研究は、生態学そのものが面白いのはもちろんのこと、他分野にも大きなインパクトを与えるポテンシャルを持った分野である。今後はさらに、微生物生態学の成果が他分野研究を発展させる原動力となるような学際研究を行いたいと考えている。若い学生には、ラボ内で実施可能な手法を基に研究テーマを考えるのではなく、微生物や研究に興味を持つ“きっかけになった思い”を基盤としてテーマを決めて欲しいと思っている。