国立研究開発法人海洋研究開発機構では、下記の公募を行っております。
海洋機能利用部門 生命理工学センター 深海バイオリソース研究グループ
特任研究員もしくはポストドクトラル研究員 公募
募集人員 1名
※締め切りは、2025年7月30日(水) 23時59分 (日本時間/JST)必着
詳しくはリンク先をご参照ください。
■日本語ページ
https://www.jamstec.go.jp/recruit/j/details/cebn20250730/
■英語ページ
https://www.jamstec.go.jp/recruit/e/details/cebn20250730/
【問い合わせ先】
国立研究開発法人海洋研究開発機構
人事部人事任用課 採用担当
recruit-app@jamstec.go.jp
このたび、明治大学農学部農学科において教員公募を行うこととなりましたので
下記の2件ご案内いたします。
【公募情報】
専門分野:アグロエコロジー(生態学的視点に基づく農地・里山の生物多様性・物質循環・環境変動適応などを含む)
募集職種:専任准教授または専任講師
所属:明治大学農学部農学科
応募締切:2025年7月18日(金)必着
詳細情報:添付PDF、または以下URLよりご確認いただけます
https://www.meiji.ac.jp/agri/recruit/6t5h7p000000cvqk-att/a1747372277095.pdf
専門分野:土地資源学(土壌と大気・水・生物との相互作用、物質循環、環境変動への応答に関する基礎・応用研究を含む)
募集職種:専任准教授または専任講師
所属:明治大学農学部農学科
応募締切:2025年7月18日(金)必着
詳細情報:添付PDF、または以下URLよりご確認いただけます
https://www.meiji.ac.jp/agri/recruit/6t5h7p000000cvqk-att/a1747372366304.pdf
茨城大学応用生物学野において教員の公募を行うこととなりましたのでご案内いたします。
【職種】
教授または准教授(任期付き)
【専門分野】
環境動態解析学、自然共生システム学、植物栄養学、土壌学、植物生産科学、環境農学に関する分野
【所属】
茨城大学応用生物学野食生命科学領域(茨城大学グリーンバイオテクノロジー研究センター専任教員)
【着任時期】
2026年1月1日以降できるだけ早い時期
【応募締切】
2025年7月31日(木)(必着)
詳細は、以下のURLよりご確認いただけます:
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?id=D125051116
国際科学技術財団では若い研究者の従来枠にとらわれない挑戦、新しい展開・発展での研究を奨励し、その支援を行っています。
本年度の研究助成は「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を文系、理系を問わず、広く募集します。
(1件500万円~1000万円程度4~8件程度)
詳細につきましてはホームページに記載しております。
https://www.japanprize.jp/subsidy_yoko.html
沢山の意欲的な若手研究者のご応募を期待しております。ご案内いたします。
大隅基礎科学創成財団 第9期 研究助成公募要項
■ 助成対象
•基礎科学(一般)/・基礎科学(酵母)
■ 助成金額・件数
・【基礎科学(一般)】
o A枠:最大1,000万円/件
o B枠:最大300万円/件
採択数:合計6~10件
• 【基礎科学(酵母)】
o 最大500万円/件
採択数:3件程度
■ 助成期間
• 2025年11月~2027年10月末(2年間)
■ 応募期間
• 2025年5月7日(水)~6月30日(月)
• 期日厳守
■ 応募締切:2025年6月30日(月)
■ 募集要項・申請方法等の詳細
財団公式HP( https://www.ofsf.or.jp/activity/ )をご参照ください。
東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構では、
日程:2025年7月28日(月)~8月2日(土)
場所:東京大学農学部弥生講堂・アネックス
農学部2号館化学第一講義室
参加費:無料
参加申込:事前登録制
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/
プログラム等の詳細は微生物ウィーク2025ウェブサイトをご覧
https://park.itc.u-tokyo.ac.
7月30日(水)
日本微生物生態学会会員様 各位
陽気に恵まれ心地よい日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。
この度、株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズより、以下の通りワークショップのご案内をさせていただきます。
近年注目されているドロップレット技術はハイスループットに微生物培養や微生物産生酵素のスクリーニングを実施できる技術です。
本ワークショップではドロップレット技術の最新技術について計6名の先生方からご講演いただきます。
詳細は以下内容もしくは特設ページをご覧ください。
特設ページ: https://event.on-chip.co.jp/droplet2025 (ご登録はこちらから!!)
<DROPLET 2025 未来を創る一滴:ドロップレット技術が切り開く産業と研究の未来>
●開催日時:2025年6月20日(金) 10:00~(17:00~意見交流会開催)
●開催場所:秋葉原UDX(現地開催・ウェブ開催)
●ご登壇予定(英数50音順))
・Novartis BioMedical Research 山田 健先生
・九州大学 加隈 綾晟先生
・産業技術総合研究所 野田 尚宏先生
・産業技術総合研究所 佐々木 章先生
・水産研究・教育機構 山本 慧史先生
・理化学研究所 城口 克之先生
●キーワード:微生物・細胞スクリーニング、細菌叢解析技術、微細藻類、化合物スクリーニング、ELISA
以上、社員一同皆様のご参加を心よりお待ちしております。
東北大学と海洋研究開発機構による世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)「変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)」では、
下記の公募を行っております。
AIMEC研究員もしくはAIMECポストドクトラル研究員 2~3名
・ 海洋環境統合解析ユニット
・ 沿岸生態系サービス研究ユニット
・ 海洋地球システム統合数理解析ユニット
・ 海洋生態系モデリング評価研究ユニット
※適性により上記以外のユニットへの配属が検討される場合があります。
※締め切りは、2025年6月15日(日) 23時59分 (日本時間/JST)必着
詳しくはリンク先をご参照ください。
■日本語ページ
https://www.jamstec.go.jp/recruit/j/details/wpi20250615/
■英語ページ
https://www.jamstec.go.jp/recruit/e/details/wpi20250615/
【問い合わせ先】
変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)
研究推進企画部 採用担当
wpi-aimec_hr@jamstec.go.jp
京都大学化学研究所附属バイオインフォマティクスセンターにおい
バイオインフォマティクス分野にて特定研究員を1名募集しており
職種:特定研究員
専門分野:バイオインフォマティクス、ゲノム科学
職務内容:膣内及び子宮内膜由来の細菌叢メタゲノムデー、ラクト
バイオインフォマティクス解析。サンテ研究所、東京大学、佐賀大
不妊症及び妊娠合併症等を適応症とした次世代ラクトバチルス菌新
任期:3年
勤務地:京都大学化学研究所附属バイオインフォマティクスセンタ
応募締切:令和7年6月17日(火)
詳細は下記をご参照下さい。
https://www.kuicr.kyoto-u.ac.j
多くの方からのご応募をお待ちしております。
各位、
第37回日本Archaea研究会講演会を下記の要領にて開催いたします。皆さまの多数のご参加をお待ちしております。本講演会では若い研究者や学生さんの発表を歓迎します。大学の先生等におかれましては、学生さんの参加や発表を促していただけますよう、お願い致します。
講演日時:2025年7月17日(木)13:00 〜 7月18日(金)13:00(開始・終了時刻は予定)
講演会場:みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール
〒500-8076 岐阜市司町40番地5 (TEL 058-265-4101)
JR岐阜駅または名鉄岐阜駅からバスで約15分(下記参照)
https://g-mediacosmos.jp/access/
懇親会:7月17日(木)18:00〜20:00を予定(場所や参加費は未定)
講演会参加費(予定):一般 5000円、学生 無料
講演要領:「口頭演題A」と「口頭演題B(ショート)」を募集します。質疑応答を含む講演時間は、演題Aでは15〜20分程度、演題B(ショート)では10〜12分程度を予定しています。
発表ならびに参加申込方法:
発表や参加を希望する方は、以下のウェブ参加フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/88PvwCBXqgKoUSMk9
発表申込〆切:6月11日(水)
講演会参加申込〆切:7月9日(水)
講演要旨:〆切6月23日(月)必着(宛先 archaea.kenkyu.kai@gmail.com)
詳細は下記のホームページをご参照ください。
http://archaea.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=157796
問い合わせ先(研究会事務局):
富山県立大学工学部 金井 保、理化学研究所バイオリソース研究センター 加藤真悟
E-mail:archaea.kenkyu.kai@gmail.com
===
第37回日本Archaea研究会講演会世話人
金井保・加藤真悟・横川隆志・尾木野弘実
この度、サントリー生命科学財団では「サントリー生命科学研究者支援プログラム
SunRiSE (Suntory Rising Stars Encouragement Program in Life Sciences)」を実施します。
SunRiSEは45歳以下の若手研究者(10人)に対して、1000万円を5年間支援するものです。
・募集研究課題:分子を中心に据えた、生命現象のメカニズムの解明
・応募資格:PIもしくはPIを目指す人
現在の職位・任期の有無は不問
2025年4月1日現在で満45歳以下
海外からの応募可(日本に研究拠点を移すこと)
女性研究者の応募歓迎
・募集人数:10名
・支援額:1000万円×5年(一人あたり5000万円)
・支援期間:2026年4月~ 5年間
・応募期間:2025年5月26日~6月29日
詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.sunbor.or.jp/news/sunrise-%e7%ac%ac2%e6%9c%9f%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
お問合せ先 sunrise@sunbor.or.jp
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 幌延地圏環境研究所では、下記のとおり研究員を公募いたします。
募集人員・職種
1名 研究員
採用予定日
随時(試用期間あり)
勤務地・配属先
北海道天塩郡幌延町栄町5-3
幌延地圏環境研究所 地下微生物環境研究グループ
研究所・業務の概要
幌延地圏環境研究所は地下微生物環境研究グループ、地下水環境研究グル
ープ、堆積岩特性研究グループの3つの研究グループから構成され、現在
、地下微生物を活用した地層中未利用有機物のバイオメタン化等に関する
研究プロジェクトを推進しています。本公募は、地下微生物環境研究グル
ープの研究員を公募するものです。
(専門分野)
専門分野は、環境微生物学、微生物生態学。特に、地下環境の微生物を対
象とし、地下における炭素循環の解明を目指した基礎的な研究分野と、そ
れらの知見を基にした地下環境の有効利用に関する工学的な研究分野。募
集分野の研究目標・課題はホームページ(http://www.h-rise.jp)をご参照く
ださい。
(研究分野)
1 2 3
大分類 総合生物 工学 農学
小分類 その他 その他 農芸化学
その他 微生物生態学 その他
勤務形態
フルタイム(裁量労働制)
待 遇
(1) 任期:年度契約・更新可(詳細問合せ可)
(2) 給与:経験、能力、実績に応じて決定(社会保険の適用あり)
年収約450~550万円
(3) 就業時間 : 裁量労働制を適用
(基本始業9時、終業17時、昼休憩60分とし本人の裁量に委ねる)
(4) 休日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、
夏季休暇2日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、
これ以外の休日については当財団の就業規定に従います。
(5) 敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり)
応募資格
(1) 微生物の培養などに関する研究経験者
(2) 博士の学位を有する方(見込み含む。)
(3) 普通自動車免許保有が望ましい
応募書類
(1) 履歴書(写真貼付、研究歴記載)
(2) 研究業績リスト及び主要論文の別刷り(3編以内、コピー可)など
(3) これまでの研究概要
(1000字程度、習得した実験技術を含めて記載してください)
(4) 本人についてご意見を伺うことができる方1名の氏名と連絡先
(住所、電話番号、E-mailアドレス)
(5) 志望理由 (1000字程度)。
応募期間
応募は随時受け付けておりますが適任者が決定した場合は応募を締め切る場
合があります。
書類の提出は簡易書留、レターパック、宅配便など追跡可能な方式でお送
りください。封筒の表に「研究員応募書類在中」と朱書きしてください。
その他
・応募書類は返却いたしませんが、本選考の目的以外には使用せず、選
考終了後責任をもって処分いたします。
・幌延地圏環境研究所は、科学研究費助成事業に応募ができる機関です。
・ 一次書類選考を通った方には面接試験を行います。面接試験に該当す
る方にはご連絡を差し上げます。対面での面接試験を行いますが、状
況に応じてオンライン面接試験の可能性もあります(候補者には最終
確認させていただきます)。
問合せ先および応募書類送付先
〒098-3221北海道天塩郡幌延町栄町5-3
幌延地圏環境研究所 所長代理(事務)谷口壽宏
Tel: 01632-9-4112, Fax: 01632-9-4113
E-mail: toshihiro.taniguchi@h-rise.jp
(問合せはメールもしくは書簡でお願いします)
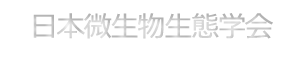

-212x300.jpg)