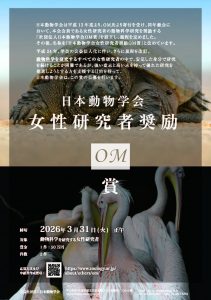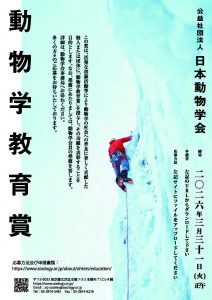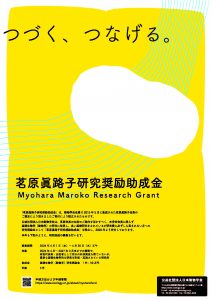東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構では、
日程:2025年7月28日(月)~8月2日(土)
場所:東京大学農学部弥生講堂・アネックス
農学部2号館化学第一講義室
参加費:無料
参加申込:事前登録制
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/
プログラム等の詳細は微生物ウィーク2025ウェブサイトをご覧
https://park.itc.u-tokyo.ac.
7月30日(水)
「先進ゲノム支援」では支援活動の一環として情報解析講習会を開催しています。今年度第2回目となる今回は、中級者向けです。プログラミング言語「Python」を用いたバイオインフォマティクス解析データの扱いやシングルセルRNA-seq解析の基礎等を中心に、以下の要領で開催いたします。本講習会は、先進ゲノム支援(PAGS)、生命情報・DDBJセンター(DDBJ)が合同で開催いたします。
■日 時:2026年2月20日(金)10:00 ~ 16:00(予定)
■会 場: Zoomウェビナー ※現地開催はございません。
■想定スキルレベル:情報解析中級者
■募集人員:オンライン参加:200名程度
• これから自分で実践的にバイオインフォマティクス関連のプログラミングをしようと考えている方。
• 基本的なLinuxコマンドやPython言語の知識を身につけていることを前提とします。
• 応募者多数の場合は、先進ゲノム支援における支援依頼者を優先します。
• 各自のPCをご用意ください(memory 8GB以上、空きHDD容量30GB以上あれば、Windows11、Mac、Linuxいずれも可)。
• 講習ではJupyter notebookを用いてPythonの講習を行います。
• 事前に必要なソフトウェア (Pythonのモジュール) を各自のPCにインストールしていただく必要があります。
■参加費用:無料
■講習会スケジュール(予定):講習内容とスケジュールは多少変更になる場合があります。
【2月20日】
10:00~10:05 講習会説明
10:05~10:30 Jupyter notebook の使い方
10:30~11:00 Numpy
11:00~12:00 表形式ファイルの処理(Pandas)
12:00~13:00 昼食休憩
13:00~14:30 Pythonを用いた基礎的なシングルセルRNA-seq解析
14:30~14:40 休憩
14:40~15:40 生成AIを用いたプログラミング等
15:40~16:00 質疑応答
■申し込み〆切:2026年2月9日(月)
■申し込み方法:
参加を希望される方は、下記リンクより詳細をご確認の上お申し込みください。
https://www.genome-sci.jp/bioinformatic#1
先進ゲノム支援事務局
国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部微生物病原学分野では、下記の公募を行っております。
助教 女性限定公募
募集人員 1名
※締め切りは、2026年2月27日(水) 17時00分 (日本時間/JST)必着
ただし,適任者の採用が決まり次第,募集を締め切ります。
詳しくはリンク先をご参照ください。
■日本語ページ
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?id=D126010226
【問い合わせ先】
徳島大学大学院医歯薬学研究部 微生物病原学分野
野間口雅子
nomaguchi@tokushima-u.ac.jp
□
■ 戦略的創造研究推進事業CRESTにおけるフランスANRとの日仏共同提案募集予告
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●募集趣旨:
戦略的創造研究推進事業CRESTの2026年度募集において、フランス国立研究機構(ANR)と連携し、以下の2領域で日仏共同提案を募集します。採択された場合、日本側グループはJST(CREST)から、フランス側グループはANRからそれぞれ支援を受けます。
●共同研究提案を募集する研究領域:
・「人とAIの共生・協働社会を実現する学際的システム基盤の創出」(研究総括:和泉 潔)
・「予測・制御のための数理科学的基盤の創出」(研究総括:小谷 元子)
●応募方法:JSTとANRの両機関に共同研究提案書(英語、CREST-ANR共通書式)を申請
※詳細は、今後、JST募集HP、ANRのHPにてご案内します。
※日仏共同提案と通常のCREST提案の両方を申請することはできません。
※なお、本予告は、国会における令和8年度政府予算の成立を前提として行っています。
●詳細URL:
[ANR] https://anr.fr/JSTCREST2026/
[JST] https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/info/info_260113.html
●問合せ先:国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略研究推進部[募集専用]
E-mail:rp-info@jst.go.jp
平素より、お世話になっております。
日本動物学会は、2026年度の下記賞及び助成の公募を実施いたします。
茗原眞路子研究奨励助成金は2026年4月より募集開始となります。
申請に関する詳細は下記URLよりご確認ください。
日本動物学会女性研究者奨励OM賞
https://www.zoology.or.jp/about/others/om
【締切】2026年3月31日(火)正午
動物学教育賞
https://www.zoology.or.jp/about/others/education
【締切】2026年3月31日(火)正午
茗原眞路子研究奨励助成金
https://www.zoology.or.jp/about/myoharafund
【募集期間】2026年4月1日(水)~4月30日(木)正午
皆さまからのご応募を心よりお待ちしております。
公益社団法人 日本動物学会
生研支援センターでは、「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」の公募を開始しました。
本事業は、スマート農業技術の開発及び供給を迅速かつ強力に推進するため、
様々な関係者が実施するスマート農業技術に係る研究開発・改良の取組を支援するものです。
■公募期間:2025年12月26日(金曜日)~2026年2月13日(金曜日)正午まで
■公募説明動画:2026年1月上中旬生研支援センターのHPにて掲載予定
▼公募要領等の詳細情報は、下記URLをご参照ください。(生研支援センターウェブサイト)
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/smart-nogyo/offering/koubo/2025-2.html
【お問い合わせ先】
生物系特定産業技術研究支援センター (生研支援センター)
事業推進部 民間技術開発課(担当:鎌田、石橋)
E-mail : brain-smartagriweb@ml.affrc.go.jp
山口大学中高温微生物研究センターは,発酵,環境,病原,共通基盤研究・開発の4部門から成り,中高温域に生育する微生物を中心に幅広い微生物を対象とした研究拠点です。
本センターでは,「低炭素化社会実現に貢献する高温発酵系の開発」,「熱帯地域に有用なバイオマス利用・新規バイオエネルギー生産系の開発」,「熱帯地域で拡大する感染症の拡大・伝播に対処する診断・予防法の確立」等の研究を進めています(センターの概要については,本センターのホームページをご覧ください。)。2018年度より,これまで以上に国内研究者との連携を活性化し,微生物研究の新たな展開や中高温微生物研究の拡大を目指して,共同研究の公募を開始いたしました。
2026年度も,以下の要領で共同研究を公募し,採択課題にはその共同研究に必要な旅費および研究費の支援を行います。本センター所有の設備,生物資源(遺伝子資源)を利用した共同研究を奨励しますので,これらの利用がある場合は申請書の「5.研究計画・方法等」の欄にその旨を明確に記載してください。なお,過去の採択課題はホームページに掲載しています。
積極的なご応募をお待ちしております。
1.課題種別と研究課題
以下の2つの共同研究を公募します。
(1) 課題設定型共同研究
中高温微生物研究を先導する課題として,2026年度は以下の二つの課題に関する共同研究を 募集します。助成金額は上限を50万円とします。ただし,採択時に減額されることもあります。
2件程度を採択する予定です。
〇熱帯・亜熱帯・温帯地域に分布する微生物を対象とした研究
熱帯・亜熱帯・温帯地域の環境中ならびに同環境に生息する動植物由来の微生物を対象とした分布地域の把握,生存戦略や感染機構の解明は,中高温微生物の基礎から応用に至る理解,利用に重要です。そこで,熱帯・亜熱帯・温帯地域に分布する古細菌,真菌,細菌,ウイルス等を対象とした新たな微生物の分離,検出法の確立や疫学調査,増殖性機序の解析,微生物の感染性・病原性・共生関係の解明,予防・治療法の確立等を目指す研究テーマを募集します。本センターが所有する微生物資源の利用も可能です。
〇微生物の耐熱性等に寄与する生体分子の構造,機能とその利用に関する研究
耐熱性をはじめとする微生物のストレス耐性機構は,環境変化への適応,特殊環境での生育,さらには物質生産の効率化など,基礎から応用まで広く微生物の理解,利用に重要です。耐性遺伝子およびそのタンパク質の機能と役割,タンパク質レベルの耐熱性,脂質構造の違いや変化,さらにはそれら分子を介した細胞レベルでの適応まで,様々な段階を介して微生物は耐性を獲得,制御していると考えられることから,これら耐性に関わる分子の構造,機能や制御系の解明を目指す
研究や,耐性を利用した物質生産系の開発などの研究テーマを募集します。本センターが所有する微生物資源の利用も可能です。
(2) 一般型共同研究
中高温微生物研究を中心に,発酵・環境・病原微生物など,幅広い微生物関連の共同研究を公募します。助成金額は上限を30万円とします。ただし,採択時に減額されることもあります。
25件程度を採択する予定です。
2.申請資格者
申請をおこなう研究代表者は,国公私立大学,公的研究機関および民間企業等に所属し,当該分野の研究に従事する教員・研究者とし,若手研究者・女性研究者を積極的に支援します。また,学振PD研究員,科研費等で雇用された博士研究員も研究代表者として申請することが可能(所属研究室の代表者および受入研究者の承認が必要)です。大学院生・大学学部生が研究代表者として申請することはできませんが,研究メンバーとして参加することは可能です。
なお,採択者には研究終了後には報告書を提出していただきます。また,共同研究者間の交流に
よる中高温微生物研究コミュニティの拡大を目的として,研究報告会を開催しています。2027年度
以降に本学で開催する本研究報告会での研究成果の発表をお願いします。
3.研究期間
2026年4月1日~2027年3月31日
なお,予算の執行は2027年3月18日(木)までに完了してください。
4.申請方法
1)申請書等の各様式は,ホームページのリンクからダウンロードしてご使用ください。
2)申請にあたり,共同研究者となる本センター教員をご記入ください。必ず事前に当該教員と研究
計画の詳細を打合せのうえ申請してください。
※申請書記入上の注意
*「年齢・性別」欄に記載の情報は,公募型共同研究の選考の他,文部科学省への報告やその他統計・調査においても,個人を特定できない形で利用します。
1.課題種別
研究テーマについて,課題設定型か一般型か希望される方を〇で囲んでください。また,課題設定型を選択し不採択の場合には,一般型で選考することも可能です。一般型での選考も希望する場合は,□にチェックを入れてください。
3.研究組織
『共同研究者名』枠の(研究メンバー)欄には,必ず本センターの担当教員を入れてください。
なお,適切なセンター担当教員が分からない場合などは,下記事務担当にご連絡ください。
4.研究の背景・目的・期待される成果
研究目的の中で,本センターの共同研究としての妥当性を示してください。
6.所要額
助成金額は,課題設定型共同研究は上限50万円,一般型共同研究は上限30万円とします。なお,減額されることもありますので,ご了承ください。
7.これまでの研究経緯と成果
継続申請の場合は,これまでの公募型共同研究の成果等について記載してください。
新規申請の場合は記載不要です。
8.本研究に関連する代表的な発表論文等
著者名・出版年・論文名・掲載誌名等の順に記載してください。また,et al.等は使用せず,申請者が著者に含まれることを明確に記載してください。
5.申請書提出期限
2026年2月20日(金)までに,下記メールアドレスへ申請書をPDFファイルでお送りください。
6.審査と審査結果の通知
提案いただいた内容は,「本センターの共同研究としての妥当性」,「研究テーマの有用性」,「目標達成の可能性や計画の妥当性」の3項目の観点から審査し,年齢・性別を考慮して,本センター公募型共同研究委員会において採否を決定します。また,継続課題については,この3項目に加えてこれまでの研究成果も審査項目に加えます。審査結果は決定後すみやかに申請者へ通知いたしま
す。
なお,原則としてホームページに採択課題・氏名・所属を掲載いたします。
国立大学法人山口大学 中高温微生物研究センター 事務担当
〒753-8515 山口県山口市吉田1677-1
TEL :083-933-5246
E-mail:agkenkyu@yamaguchi-u.ac.jp
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/yurctmr/joint_research__trashed/index.html
国立研究開発法人海洋研究開発機構では、下記の公募を行っております。
超先鋭研究開発部門 超先鋭研究開発プログラム
特任准研究員 公募
募集人員 1名
※締め切りは、2026年1月5日(月) 23時59分 (日本時間/JST)必着
詳しくはリンク先をご参照ください。
https://www.jamstec.go.jp/recruit/j/details/sugar20260105/
【問い合わせ先】
国立研究開発法人海洋研究開発機構
管理部門人事部人事任用課 採用担当
recruit-app@jamstec.go.jp
日本微生物生態学会は、会則附則 6 に基づき日本微生物生態学会学会賞、日本微生物生態学会奨励賞、日本
微生物生態学会若手賞 (以下、学会賞、奨励賞、若手賞) を授与します。学会賞は微生物生態学分野における
顕著な学術的業績を有する他、本学会の発展・運営へ大きく貢献し、今後の微生物生態学分野のさらなる発展に
向けたリーダーシップが期待される正会員を授賞対象者とします。奨励賞は海外における Young Scientist
Award に相当します。具体的には、微生物生態学会がカバーする様々な学術領域において、「学術的に優れた一
連の研究に基づく論文を発表し、正会員として本学会の諸活動にも貢献し、今後一層の活躍が期待できる若手研
究者」を広く授賞対象者とします。また、さらなる若手研究者の奨励を目指して昨年度から若手賞を創設しました。
若手賞授賞の選考基準は上記奨励賞と同様ですが、若手賞の授賞対象者は原則として学位取得後 8 年以内の
研究者、奨励賞の授賞対象者は原則として学位取得後 8 年から 18 年以内の研究者とすることで、より多くの若
手研究者、特に学位取得後間もない研究者に対して受賞機会を拡大します。
今回、下記の要領で第 4 回学会賞、第 12 回奨励賞、ならびに第 4 回若手賞授賞候補者の推薦を募集いたしま
すので、多くの皆様からの積極的なご応募をお待ちしています。応募内容は各賞選考委員会において厳正に検討
され、最終的に若干名の各賞授賞候補者を決定いたします。
【提出資料】
(1) 推薦者の氏名、所属、連絡先(自薦の場合は不要)
(2) 被推薦者の氏名、年齢(生年月日)、所属、職名、連絡先、学部以降の略歴・学位取得年・職歴および推薦対
象とする賞の種類
(3) 被推薦者の日本微生物生態学会に関する情報(入会年、会員番号、主な活動実績(役職、企画等)),
Microbes and Environments および日本微生物生態学会誌発表論文数
(4) 被推薦者の論文出版状況が分かるウェブサイトがあればその URL
(5) 推薦理由書(1000 字以内)
(6) 研究内容説明書(2000 字以内、研究内容全体を表す題目を冒頭に付してください)
(7) 業績(査読付き原著論文、総説、著書、国際学会発表、招待講演など)リスト。本推薦の研究内容に関連する
ものに○を付し、査読付き原著論文には被引用数(WoS や Scopus など使用したデータベース名を明記すること)
を記す。
(8) 特筆すべき関連業績 5 編以内(業績リストに◎を付す)の別刷り
以上(1)〜(8)を PDF 形式の電子ファイル(ファイルサイズは 10Mb 以内)としてとりまとめたものを日本微生物生
態学会事務局のメールアドレスにお送りください。
【締切り】
令和 8 年 1 月 31 日(土)(必着)
【問合せ先】
日本微生物生態学会事務局 office[at]microbial-ecology.jp
([at]は@マークで置き換えてください
学会員の皆様へ
日頃より本学会の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
5学会の共同編集学術誌であるMicrobes and Environmentsの国際的な認知度の向上を目指し、2023年度から2027年度の5年間にわたり「独創的論文・研究者の取り込み強化と掲載論文の社会的発信力向上によるリ・ブランディング活動を通じたMicrobes and Environment 誌の新たな国際情報発信強化」という取り組みで日本学術振興会から科学研究費補助金(研究成果公開促進費・国際情報発信強化)の補助を受けています。
このたび当事業の中間評価が行われ、論文の社会的注目度を示すAltmetrics 値の向上、国際的な共同査読システムPCI Microbiologyへの参加、特集号の発行などが高く評価され、A評価をいただくことができました。引き続き、編集委員会を中心に本取り組みを推進してまいります。今後とも、共同編集学会員の皆様からのMicrobes and Environmentsへの論文の投稿をお待ちしております。
日本微生物生態学会 会長 二又裕之
東京大学大気海洋研究所と海洋研究開発機構は、研究船等を利用して得られた成果の報告会として
「海と地球のシンポジウム2025」を2026年3月10日〜11日に開催します。
研究船等を利用された皆様、こちらのシンポジウムにて航海速報や研究成果などをご発表ください。
また多くの皆様のご参加をお待ちしております。
「海と地球のシンポジウム2025」
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/
・開催日時:1日目 2026年3月10日(火)
2日目 2026年3月11日(水)
*3/10(1日目)の夕方に懇親会を予定してま
*2日目の閉会式に”学生優秀発表賞”の表彰式を行う予定です。
・会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
〇発表課題登録〆切まであと5日!:下記ホームページより登録をお願いします。
主席研究員・首席研究者および乗船課題に関係する研究者の皆さま、発表課題のご応募をお待ちしております。
・締切:2025年12月12日(金)
・応募方法:下記の「発表課題募集」ページにて応募フォームを使用してご応募ください。
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/invitation.html
Confitアカウントにてログイン後、参加区分等を指定し、登録を完了させてください。
登録完了後に、自動送信にて参加に関する確認メールが届きます。
※上記のHPにて同時に「参加登録」および「懇親会の参加登録」ができます。
〇懇親会の参加登録:以下Googleフォームから直接「参加登録」も可能です。
https://forms.gle/ARySLEduEtiRiy6G9
Google フォームに必要事項をご記載の上ご投稿ください。
完了後、自動送信にて懇親会参加に関する確認メールが届きます。
国立研究開発法人海洋研究開発機構では、
超先鋭研究開発部門 超先鋭研究開発プログラム
特任研究員もしくはポストドクトラル研究員 公募
募集人員 1名
※締め切りは、2025年12月24日(水) 23時59分 (日本時間/JST)必着
詳しくはリンク先をご参照ください。
■日本語ページ
https://www.jamstec.go.jp/
■英語ページ
https://www.jamstec.go.jp/
【問い合わせ先】
国立研究開発法人海洋研究開発機構
管理部門人事部人事任用課 採用担当
recruit-app@jamstec.go.jp
Asia-Pacific Biofilms 2026 invites the submission of abstracts on all aspects of biofilm research. Highlighted topics for consideration include:
(1) Bioinformatic analysis of biofilms;
(2) Mechanisms of biofilm development and antimicrobial resistance;
(3) Biofilm control and novel therapeutic strategies;
(4) Communication and signaling factors in biofilms;
(5) Rapid detection and diagnostic applications for biofilm forming bacteria;
(6) Virulence and toxins in clinical biofilms;
(7) Evolution and stress tolerance in biofilms;
(8) Industrial, environmental and applied biofilms research.
The conference will feature three outstanding plenary speakers in the field:
Gordon Ramage speaking about “The Clinical Impact of Fungal and Interkingdom Biofilms”
Cynthia Whitchurch FAA with a talk entitled “When death becomes a biofilm: autolytic programmed cell death in biofilms”
Marvin Whiteley TBD
The link for registrations and abstract submissions can be found
here: https://www.asiapacificbiofilms.org/2026/.
Early Abstract Submission Deadline: December 15, 2025
Abstracts submitted by this date will receive notification of acceptance for either a talk or poster before the end of the year.
Final Abstract Submission Deadline: February 14th, 2026
Submissions will continue to be accepted until this date, but early submissions are strongly encouraged. Abstracts submitted by this date will receive notification of acceptance for either a talk or poster by the 1st of March.
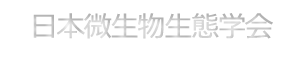

-212x300.jpg)